上野駅・京成上野駅
Spot
(上野公園の博物館・美術館)
.jpg)
東京国立博物館
とうきょうこくりつはくぶつかん
上野駅から約500m
京成上野駅から約800m
1872年に創設された日本最古の博物館、通称「トーハク」。本館・平成館・東洋館・法隆寺宝物館・黒田記念館・表慶館の6つの建物で構成され、150年にわたり受け継いできた収蔵品は約12万件を超える。総合文化展の展示室はほぼ毎週一部を年間300回変えている。展示品は個人利用に限り撮影可能。撮影禁止のものあり。
.jpg) 左はトーハクくん、右がユリノキちゃん。トーハクくんの本名は「東博(あずまひろし)」、ユリノキちゃんは「ノキ ユリ」
左はトーハクくん、右がユリノキちゃん。トーハクくんの本名は「東博(あずまひろし)」、ユリノキちゃんは「ノキ ユリ」
.jpg) 本館前にあるユリノキは明治14年に植えられ、5月中旬にチューリップのような花を咲かせる
本館前にあるユリノキは明治14年に植えられ、5月中旬にチューリップのような花を咲かせる
.jpg) 本館2階にある貴賓室(きひんしつ)。便殿(びんでん)とも呼ばれ、中国では貴人が休息するための仮の御殿を意味する。現在は国の大事な来客の休憩室として使用されている
本館2階にある貴賓室(きひんしつ)。便殿(びんでん)とも呼ばれ、中国では貴人が休息するための仮の御殿を意味する。現在は国の大事な来客の休憩室として使用されている
.jpg) 日本の考古と特別展を開催する平成館。1999年会館
日本の考古と特別展を開催する平成館。1999年会館
.jpg) 1909年に開館した表慶館(ひょうけいかん)。皇太子のご成婚を記念して計画された建物で重要文化財。中は特別展
1909年に開館した表慶館(ひょうけいかん)。皇太子のご成婚を記念して計画された建物で重要文化財。中は特別展
.jpg) 黒田家の江戸屋敷鬼瓦。徳川幕府の参勤交代の制度により、江戸には諸大名の屋敷が設けられた。筑前福岡藩主黒田家の建物の棟飾りとして用いられた鬼瓦である
黒田家の江戸屋敷鬼瓦。徳川幕府の参勤交代の制度により、江戸には諸大名の屋敷が設けられた。筑前福岡藩主黒田家の建物の棟飾りとして用いられた鬼瓦である
.jpg) 旧因州池田屋敷表門(きゅういんしゅういけだやしきおもてもん)。因州池田江戸屋敷の表門で、形式と手法から見て大名屋敷表門として最も格式が高い
旧因州池田屋敷表門(きゅういんしゅういけだやしきおもてもん)。因州池田江戸屋敷の表門で、形式と手法から見て大名屋敷表門として最も格式が高い
.jpg) 法隆寺宝物館、東京国立博物館の所有する法隆寺献納宝物を保存・展示するために1964年に開館。1999年に高い保存機能を備えた新宝物館になった
法隆寺宝物館、東京国立博物館の所有する法隆寺献納宝物を保存・展示するために1964年に開館。1999年に高い保存機能を備えた新宝物館になった
.jpg) 本館の後ろにある庭園。5棟の茶室が点在し、春になるとソメイヨシノやオオシマザクラなど10種類のも桜が開花する
本館の後ろにある庭園。5棟の茶室が点在し、春になるとソメイヨシノやオオシマザクラなど10種類のも桜が開花する
.jpg) 九条館(くじょうかん)。京都御所内の九条邸にあったものを東京赤坂の九条邸に移した建築で、当主の居室として使われていた。1934年に寄贈され現在の位置に移築される
九条館(くじょうかん)。京都御所内の九条邸にあったものを東京赤坂の九条邸に移した建築で、当主の居室として使われていた。1934年に寄贈され現在の位置に移築される
.jpg) 応挙館(おうきょかん)。名古屋市郊外の明眼院の書院として1742年に建築、一度東京品川の益田孝(ますだたかし)邸内に移築され、1933年に当館に寄贈され移築される
応挙館(おうきょかん)。名古屋市郊外の明眼院の書院として1742年に建築、一度東京品川の益田孝(ますだたかし)邸内に移築され、1933年に当館に寄贈され移築される
.jpg) 六窓庵(ろくそうあん)。奈良の興福寺慈眼院(こうふくじじげんいん)に建てられ、現在の奈良国立博物館にある八窓庵などと共に大和の三大茶室と呼ばれた。1875年に当館が購入して移築した
六窓庵(ろくそうあん)。奈良の興福寺慈眼院(こうふくじじげんいん)に建てられ、現在の奈良国立博物館にある八窓庵などと共に大和の三大茶室と呼ばれた。1875年に当館が購入して移築した
.jpg) 転合庵(てんごうあん)。小堀遠州が八条宮から茶入を賜った際に、披露するために京都伏見に建てられた。1963年に当館に寄贈される
転合庵(てんごうあん)。小堀遠州が八条宮から茶入を賜った際に、披露するために京都伏見に建てられた。1963年に当館に寄贈される
.jpg) 春草廬(しゅんそうろ)。河村瑞賢(かわむらずいけん)が摂津淀川改修工事の際に建てた休憩所。1959年に当館に寄贈された
春草廬(しゅんそうろ)。河村瑞賢(かわむらずいけん)が摂津淀川改修工事の際に建てた休憩所。1959年に当館に寄贈された
.jpg) 1968年に開館した東洋館。中国や朝鮮半島などの美術品を展示する
1968年に開館した東洋館。中国や朝鮮半島などの美術品を展示する
.jpg) ミュージアムショップで販売されるものは、日本全国の美術館や博物館で販売されるオリジナルグッズの先駆け的存在とも言われる
ミュージアムショップで販売されるものは、日本全国の美術館や博物館で販売されるオリジナルグッズの先駆け的存在とも言われる
.jpg)
国立科学博物館
こくりつかがくはくぶつかん
上野駅から約450m
京成上野駅から約700m
上野恩賜公園内に立地。自然史、自然に関する化学技術の研究および調査、資料の収集を行う。施設は計3か所に分散しており東京都台東区の上野本館、港区の附属自然教育園、茨城県つくば市のつくば植物園があり、上野は本館と地球館の2棟の建物で構成されている。館内の撮影は個人利用に限り可。
.jpg) シロナガスクジラのモニュメント
シロナガスクジラのモニュメント
.jpg) 知恵ふくろうとも呼ばれる大型鋳造地球儀。大型の美術品などをつくる際に使われる「フルモールド鋳造」技術で作成された
知恵ふくろうとも呼ばれる大型鋳造地球儀。大型の美術品などをつくる際に使われる「フルモールド鋳造」技術で作成された
.jpg) 本館内は装飾が美しい
本館内は装飾が美しい
.jpg) 地球館屋上「ハーブガーデン」
地球館屋上「ハーブガーデン」
.jpg) ミュージアムショップ
ミュージアムショップ
.jpg) 博物館の裏側にあるラムダロケット用ランチャー。日本初の人工衛星「おおすみ」の打ち上げに使用され一連の実験の後、当館に移管・展示を行った
博物館の裏側にあるラムダロケット用ランチャー。日本初の人工衛星「おおすみ」の打ち上げに使用され一連の実験の後、当館に移管・展示を行った
.jpg)
東京都美術館
とうきょうとびじゅつかん
上野駅から約550m
京成上野駅から約700m
略称は「都美」。1926年に「都民のための美術の振興を図る」目的で開館した日本初の公立美術館。「アートへの入口」を基本方針に様々な展覧会が開かれる。秋に展覧会が多く開かれた経歴から「芸術の秋」の由来になったとも言われている。
.jpg) 展覧会により無料か有料かは異なる。有料だと料金も異なる
展覧会により無料か有料かは異なる。有料だと料金も異なる
.jpg) 800個のレモン石鹸。自由に持ち帰ることができ、持ち帰った跡は誰かがいた痕跡を伝えてくれる
800個のレモン石鹸。自由に持ち帰ることができ、持ち帰った跡は誰かがいた痕跡を伝えてくれる
.jpg) 時代の肖像 -無明・滅亡の目次録
時代の肖像 -無明・滅亡の目次録
.jpg) 紙コップのインスタレーション
紙コップのインスタレーション
.jpg) 全視の目
全視の目
.jpg) 夜の上野駅周辺の様子を監視している?
夜の上野駅周辺の様子を監視している?
.jpg) 無題。作品タイトルが「無題」
無題。作品タイトルが「無題」
.jpg) 一歩前へ
一歩前へ
.jpg)
上野の森美術館
うえののもりびじゅつかん
上野駅から約300m
京成上野駅から約300m
1972年開館。常設展を持たない企画展と特別展専用の美術館で、上野公園内にある美術館・博物館の中で唯一の私立美術館。展示内容によって無料か有料、写真撮影可能か禁止かは変わる。
.jpg) 第40回 上野の森美術館大賞展
第40回 上野の森美術館大賞展
.jpg) 壁を育てる
壁を育てる
.jpg) 水田/象潟町(きさかたまち)横岡
水田/象潟町(きさかたまち)横岡
.jpg) 明日の忘れ物を探す日
明日の忘れ物を探す日
.jpg) 砂漠の幻想
砂漠の幻想
.jpg) 吸い殻
吸い殻
.jpg)
下町風俗資料館
したまちふうぞくしりょうかん
上野駅から約300m
京成上野駅から約200m
上野周辺など下町と呼ばれる地域には明治〜大正頃まで江戸の名残があったが1923年に発生した関東大震災、震災による復興、東京オリンピック開催による契機で再開発が進行し古い時代のものはほとんどなくなってしまった。この資料館は失われつつある下町文化の記憶を次の世代に伝える目的で開館した。館内は個人利用に限り撮影ができる。
.jpg)
国立西洋美術館
こくりつせいようびじゅつかん
上野駅から約100m
京成上野駅から約500m
西洋の美術品を専門に公開する美術館。1959年にフランス政府から日本へ寄贈返還された「松方コレクション」を保存・公開する目的で開館した。本館の設計は世界的に有名な建築家「ル・コルビュジエ」の手によるもので日本唯一のものであり、世界文化遺産に登録されている。
.jpg) 考える人
考える人
.jpg) 弓をひくヘラクレス
弓をひくヘラクレス
.jpg) 地獄の門
地獄の門
.jpg) 三連祭壇画:キリスト磔刑。中央パネルと開閉可能な左右の翼部で構成される作品を「三連祭壇画(トリプティック)」と言う
三連祭壇画:キリスト磔刑。中央パネルと開閉可能な左右の翼部で構成される作品を「三連祭壇画(トリプティック)」と言う
.jpg) 悲しみの聖母。鮮やかで深みのある色彩と緻密な描写を特徴とし、冷ややかながらも甘美な愁いを帯びている
悲しみの聖母。鮮やかで深みのある色彩と緻密な描写を特徴とし、冷ややかながらも甘美な愁いを帯びている
.jpg) 静物。ビンやコップなどの日常生活のモチーフが描かれた静物画
静物。ビンやコップなどの日常生活のモチーフが描かれた静物画
.jpg)
旧東京音楽学校奏楽堂
きゅうとうきょうおんがくがっこう
そうがくどう
上野駅から約600m
京成上野駅から約900m
東京芸術大学音楽学部の前身である東京音楽学校の演奏会場。1890年建設。老朽化に伴い上野公園内に移築・復元され現在は定期的にコンサートが行われる会場として活用されている。日本最古の洋式音楽ホールとして国の重要文化財に指定されており、ホール内には日本最古のコンサート用パイプオルガンがある。
.jpg) 当館中央の軒先ペディメントには楽器をあしらった彫刻が施される。中央に火焔太鼓、左にハープ、右に笙(しょう)を配し、和と洋の音楽を取り入れ新しい音楽の創造を目指すという東京音楽学校の理念を表している
当館中央の軒先ペディメントには楽器をあしらった彫刻が施される。中央に火焔太鼓、左にハープ、右に笙(しょう)を配し、和と洋の音楽を取り入れ新しい音楽の創造を目指すという東京音楽学校の理念を表している
.jpg) ブリュートナーピアノ。ハンマーで打って発音する三本の基本弦の他に四本目の共鳴弦が張られている「アリコットシステム」が採用されている。四本目の弦の共鳴作用により、中音から深みのあるあでやかな音色と豊かな響きがある
ブリュートナーピアノ。ハンマーで打って発音する三本の基本弦の他に四本目の共鳴弦が張られている「アリコットシステム」が採用されている。四本目の弦の共鳴作用により、中音から深みのあるあでやかな音色と豊かな響きがある
.jpg) 2階の音楽ホール「奏楽堂」の漆喰壁の中には藁束(わらたば)がぎっしり詰まっている。防音や音響上の効果を狙って詰めたものだと考えられている
2階の音楽ホール「奏楽堂」の漆喰壁の中には藁束(わらたば)がぎっしり詰まっている。防音や音響上の効果を狙って詰めたものだと考えられている
.jpg) 車寄せ及び正面玄関の柱を支えた定期柱の脚部。これは明治34年頃の修復時に補修材として使用された
車寄せ及び正面玄関の柱を支えた定期柱の脚部。これは明治34年頃の修復時に補修材として使用された
.jpg) 奏楽堂。木曜日に東京藝術大学の学生によるコンサート、日曜日にチェンバロやパイプオルガンのコンサートが行われている。客席は338席
奏楽堂。木曜日に東京藝術大学の学生によるコンサート、日曜日にチェンバロやパイプオルガンのコンサートが行われている。客席は338席
.jpg)
東京藝術大学大学美術館
とうきょうげいじゅつだいがく
だいがくびじゅつかん
上野駅から約700m
京成上野駅から約1km
東京藝術大学美術学部構内にある美術館。東京藝術大学の前身である東京美術学校が学生の参考資料として、開校前から美術品を収集していたことから多くのコレクションを持ち公開を行っている。また美術学校であることから歴代教官や卒業生の作品も収蔵展示している。営利目的での撮影はできない。
←NEXT→
上野駅
京成上野駅

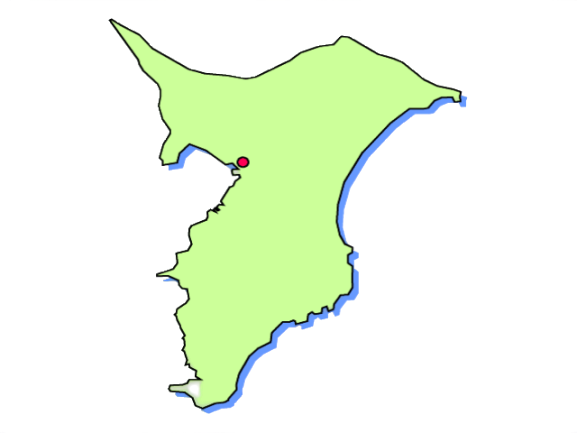 トップページ
トップページ 路線
路線 常磐線
常磐線 常磐線
常磐線 横須賀・
横須賀・ 中央・
中央・ 武蔵野線
武蔵野線 京葉線
京葉線 東武アーバン
東武アーバン つくば
つくば 京成線
京成線 北総線・
北総線・ 都営新宿線
都営新宿線 東京メトロ
東京メトロ 東葉高速線
東葉高速線 流鉄流山線
流鉄流山線 ディズニー
ディズニー ユーカリが丘線
ユーカリが丘線 千葉都市モノレール
千葉都市モノレール 東金線
東金線 鹿島線
鹿島線 銚子電気鉄道線
銚子電気鉄道線 内房線
内房線 久留里線
久留里線 小湊鉄道線
小湊鉄道線 いすみ鉄道線
いすみ鉄道線 車両図鑑
車両図鑑 発車標レア表記集
発車標レア表記集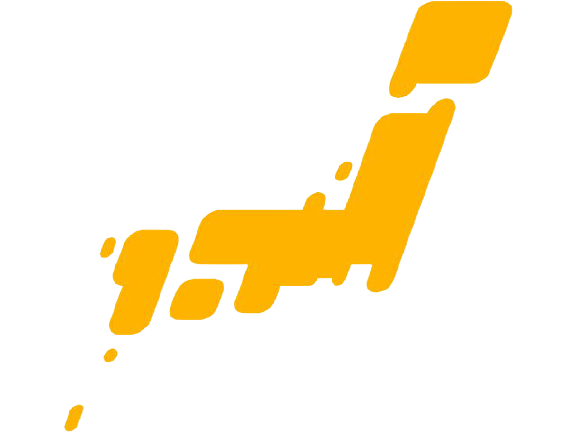 日本全国の駅
日本全国の駅



