.jpg)
市川大門
いちかわだいもん
Ichikawadaimon
中華風の独特な外観
JR東海
身延線(富士起点)69.8km
開業日 1927年(昭和2年)12月17日
中華風の駅舎は市川大門下地区公民館との合築となっていて、駅の機能のほか町民が利用可能な調理実習室や風呂場などがある。駅は市川三郷町による簡易委託の有人駅だったが2024年4月1日より無人化されたため立派な駅舎はほぼ公民館としての機能しかない。
中華風の特徴的な外観をしているが、これは町内にある大門碑林公園に意識したデザインである。和紙生産が盛んな市川三郷町は書道の手本となる中国の古文書や石碑を復元して大門碑林公園で公開を行っている。因みに公園の最寄り駅は当駅ではなく、市川本町駅である。
特急ふじかわ停車駅。当駅は甲府駅から30km圏内なため、当駅から自由席特急券を甲府駅まで買うと自由席特急料金が330円(2025年現在)とJR東海のお得な特急料金が適用される。
毎年8月7日に開催される神明の花火大会の会場は当駅が最寄り。花火大会当日は甲府方面から当日発着の臨時列車が運行される。
駅周辺
西側1km地点にに釜無川と笛吹川が平行して流れ、笛吹川の河川敷に神明の花火会場がある。
Stamp
.jpg)
| 設置場所 | 改札外 |
|---|---|
| 備考 | 廃止 |
8月7日 神明の花火。訪問時、スタンプは廃止されていたが残っていたスタンプ台に綺麗に押されたものがあったので、それを撮った。神明の花火とは市川三郷町にて毎年8月7日に開催される花火大会。当駅から徒歩約10分の河川敷を会場とする。身延線では臨時列車が設定され、定期にはない甲府始発市川大門行きなどを運行する。
.jpg)
| 設置場所 | WEBアプリ「TRAIN TRIP」で入手 |
|---|
神明の花火大会。江戸時代には日本三大花火の一つと称された市川三郷町の花火大会。起源は平安時代、源義清が甲斐国に赴任し館を構えた際、京都から義清の家臣である甚左衛門が同地に館を構える事になる。紙工でもあった甚左衛門は同地で和紙を作っていた者に技術を教え、市川和紙として一大地場産業に発展。戦国時代になると武田信玄の「のろし」の生産地となり、市川大門地区の住人は市川和紙の発展に貢献した甚左衛門を祭るためのろしの技術を活かして花火を作り、命日の7月20日に打ち上げたことが市川の花火の始まりと言われている。
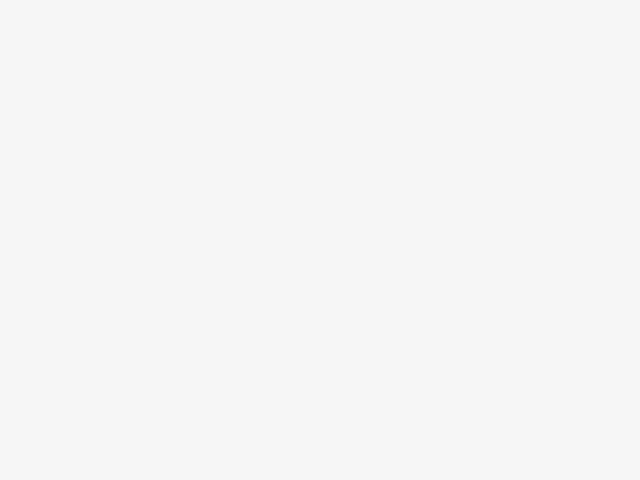
Gallery
.jpg) 駅名標
駅名標
.jpg) 縦型駅名標
縦型駅名標
.jpg) ホーム。特急ふじかわが停車する。隣の鰍沢口駅にも停車する
ホーム。特急ふじかわが停車する。隣の鰍沢口駅にも停車する
.jpg)
.jpg) 駅舎の中。無人駅で待合室としての機能しかない
駅舎の中。無人駅で待合室としての機能しかない
.jpg) 駅スタンプがあったようだが、現在は未設置。台の上に綺麗に押してあるのがあったので、それを撮って押したことに
駅スタンプがあったようだが、現在は未設置。台の上に綺麗に押してあるのがあったので、それを撮って押したことに
.jpg) トイレ、市川大門下地区公民館。誰もいない
トイレ、市川大門下地区公民館。誰もいない
.jpg) 静かな駅前。駅前にコンビニはない。当駅のデザインモチーフとなった大門碑林公園は、市川本町駅の方が近い
静かな駅前。駅前にコンビニはない。当駅のデザインモチーフとなった大門碑林公園は、市川本町駅の方が近い
.jpg) 市川三郷町観光案内図。大門碑林公園、神明の花火大会、四尾連湖など
市川三郷町観光案内図。大門碑林公園、神明の花火大会、四尾連湖など
.jpg) 駅舎全景。こんな立派なのに無人駅
駅舎全景。こんな立派なのに無人駅
.jpg) 駅の看板
駅の看板

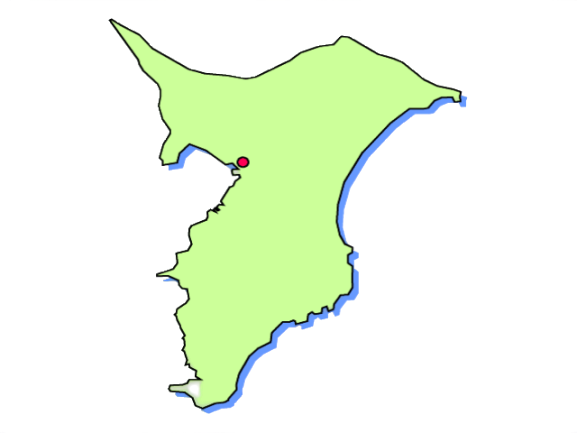 トップページ
トップページ 路線
路線 常磐線
常磐線 常磐線
常磐線 横須賀・
横須賀・ 中央・
中央・ 武蔵野線
武蔵野線 京葉線
京葉線 東武アーバン
東武アーバン つくば
つくば 京成線
京成線 北総線・
北総線・ 都営新宿線
都営新宿線 東京メトロ
東京メトロ 東葉高速線
東葉高速線 流鉄流山線
流鉄流山線 ディズニー
ディズニー ユーカリが丘線
ユーカリが丘線 千葉都市モノレール
千葉都市モノレール 東金線
東金線 鹿島線
鹿島線 銚子電気鉄道線
銚子電気鉄道線 内房線
内房線 久留里線
久留里線 小湊鉄道線
小湊鉄道線 いすみ鉄道線
いすみ鉄道線 車両図鑑
車両図鑑 発車標レア表記集
発車標レア表記集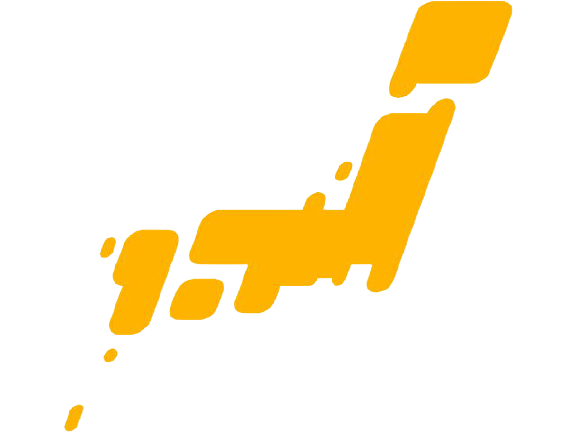 日本全国の駅
日本全国の駅