.jpg)
上毛高原
じょうもうこうげん
Jomo-Kogen
仮称のまま40年
JR東日本
上越新幹線(大宮起点)121.3km
開業日 1982年(昭和57年)11月15日
駅名の上毛高原とは実在しない地名。建設当時は月夜野という地名から「月夜野」、 みなかみ町を中心とする観光地の名称「奥利根」などの案が検討されたが、当駅は県北観光地の玄関口の機能を持ち、その範囲は日光、尾瀬、沼田、谷川、四万、草津まで及ぶことから、その広域性を意味する「上毛高原」を採用したという。仮称の駅名が採用されてから40年たった今も、変わらずそのままである。
当駅のあるみなかみ町は上毛高原駅の改名を求めている。観光業においてマイナスに働いているということで、みなかみ町はJR東日本高崎支社に対して「みなかみ」を含む地域名を入れて駅名変更するよう要望しているが、そう容易ではない模様。
上越新幹線高崎以北において唯一の新幹線単独駅。利用客は少なめ。たにがわはすべて停車、ときは一部停車する。当駅は比較的近隣にある上越線「後閑駅」の営業キロを準用する特例が設けられていて、当駅もしくは後閑駅までの"乗車券の運賃"は同じである。
2025年8月25日より発車メロディーが「JRE-IKSTシリーズ」に変更された。
駅周辺
南東にある上越線「後閑駅」までバス利用で約15分。あちらはみなかみ町中心部である。新幹線駅でありながら駅前は自然豊かで、西口すぐの場所に月夜野ホタルの里という北関東一の自然発生数を誇るホタルの名所がある。
Tracks map
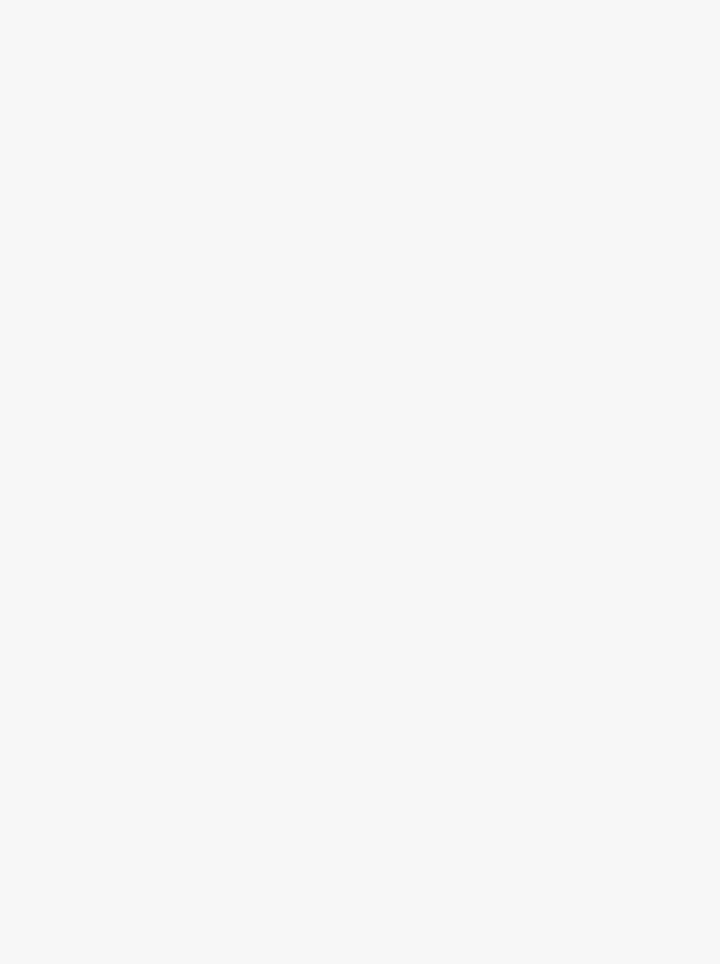
Stamp
.jpg)
| 設置場所 | 改札内 |
|---|---|
ホタルの里。当駅西口から徒歩約8分、月夜野ホタルの里はみなかみ町のホタル鑑賞スポット。北関東一の規模を誇るホタルの自然生息地。2kmの遊歩道を散策しながら小さな光を発するホタルを鑑賞することができる。見頃は6月中旬から7月上旬までとされている。
.jpg)
| 設置場所 | WEBアプリ「TRAIN TRIP」で入手 |
|---|
ホタル。みなかみ町では各所で例年6月中旬から7月中旬にかけてホタルを見ることができ、観光資源として機能している。ホタルは時間に正確で20時頃になると光を発しながら飛び始め、21時頃に落ち着いてくるという。蒸し暑い夜で月の灯りがない夜に比較的多く飛ぶらしい。
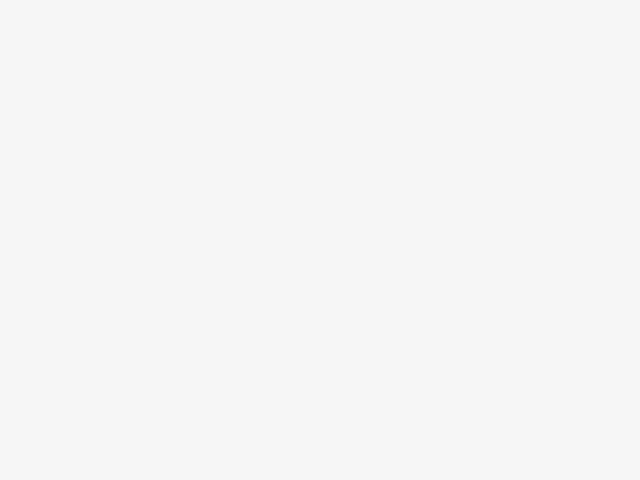
Gallery
.jpg) 駅名標。群馬デスティネーションキャンペーンのロゴ入り
駅名標。群馬デスティネーションキャンペーンのロゴ入り
.jpg) 駅名標2
駅名標2
.jpg) 縦型駅名標
縦型駅名標
.jpg) 縦型駅名標2
縦型駅名標2
.jpg) ホーム。ホームに接する副本線の間に通過線を持つ
ホーム。ホームに接する副本線の間に通過線を持つ
.jpg) ホーム越後湯沢寄りにある待合室
ホーム越後湯沢寄りにある待合室
.jpg) 改札階ののりば案内。下に谷川岳と上毛高原駅の文字
改札階ののりば案内。下に谷川岳と上毛高原駅の文字
.jpg) 自由席方向、指定席方向
自由席方向、指定席方向
.jpg)
.jpg)
.jpg) フォトスポット
フォトスポット
.jpg) 階段アート
階段アート
.jpg) 駅構内の至る所に蛍子ちゃん
駅構内の至る所に蛍子ちゃん
.jpg) 蛍子神社。蛍子ちゃんが恋愛成就を叶えてくれる
蛍子神社。蛍子ちゃんが恋愛成就を叶えてくれる
.jpg) 改札内のトイレ。みなかみ町の観光名所を描いたものか
改札内のトイレ。みなかみ町の観光名所を描いたものか
.jpg) 改札。利用客が少ないことが一目でわかる自動改札機の数
改札。利用客が少ないことが一目でわかる自動改札機の数
.jpg) 利根沼田広域案内所。訪問時は上毛高原駅工事中のため臨時休業だった
利根沼田広域案内所。訪問時は上毛高原駅工事中のため臨時休業だった
.jpg) イヌワシストア。みなかみの豊かな自然の象徴「イヌワシ」をモチーフに、町の魅力を発信するコーヒースタンド
イヌワシストア。みなかみの豊かな自然の象徴「イヌワシ」をモチーフに、町の魅力を発信するコーヒースタンド
.jpg) 改札外にあるニューデイズ上毛高原1号
改札外にあるニューデイズ上毛高原1号
.jpg) スノーボーダーの撮影パネル、提灯
スノーボーダーの撮影パネル、提灯
.jpg) 泉極志(せんごくし)。群馬県水上温泉郷公認、群馬県みなかみ町を舞台とした激烈温泉バトルファンタジー
泉極志(せんごくし)。群馬県水上温泉郷公認、群馬県みなかみ町を舞台とした激烈温泉バトルファンタジー
.jpg) WELCOME!!みなかみ町
WELCOME!!みなかみ町
.jpg)
.jpg) 谷川連峰に降り積もる雨や雪が地中に浸透し、ろ過されることでまろやかな軟水に。その湧水の取水基地が当駅高架下に設置されているらしい
谷川連峰に降り積もる雨や雪が地中に浸透し、ろ過されることでまろやかな軟水に。その湧水の取水基地が当駅高架下に設置されているらしい
.jpg) 上毛高原そば、営業時間外。日中のみの営業。関東地方における立ち食いそばで最難関、訪問困難店として有名らしい
上毛高原そば、営業時間外。日中のみの営業。関東地方における立ち食いそばで最難関、訪問困難店として有名らしい
.jpg) 東口。上越線「後閑駅」までの連絡バスが出ている。上毛高原駅の営業キロは後閑駅と同じ扱いになっている
東口。上越線「後閑駅」までの連絡バスが出ている。上毛高原駅の営業キロは後閑駅と同じ扱いになっている
.jpg)
.jpg) 東口。駅前広場はない。月夜野ホタルの里まで徒歩約8分
東口。駅前広場はない。月夜野ホタルの里まで徒歩約8分
.jpg) 東口出入口
東口出入口
.jpg) 上毛高原駅の文字
上毛高原駅の文字

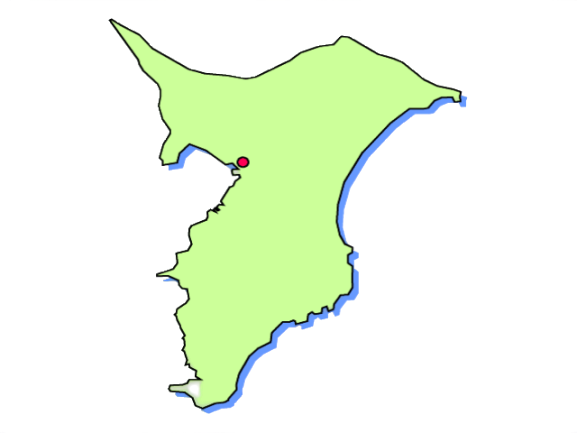 トップページ
トップページ 路線
路線 常磐線
常磐線 常磐線
常磐線 横須賀・
横須賀・ 中央・
中央・ 武蔵野線
武蔵野線 京葉線
京葉線 東武アーバン
東武アーバン つくば
つくば 京成線
京成線 北総線・
北総線・ 都営新宿線
都営新宿線 東京メトロ
東京メトロ 東葉高速線
東葉高速線 流鉄流山線
流鉄流山線 ディズニー
ディズニー ユーカリが丘線
ユーカリが丘線 千葉都市モノレール
千葉都市モノレール 東金線
東金線 鹿島線
鹿島線 銚子電気鉄道線
銚子電気鉄道線 内房線
内房線 久留里線
久留里線 小湊鉄道線
小湊鉄道線 いすみ鉄道線
いすみ鉄道線 車両図鑑
車両図鑑 発車標レア表記集
発車標レア表記集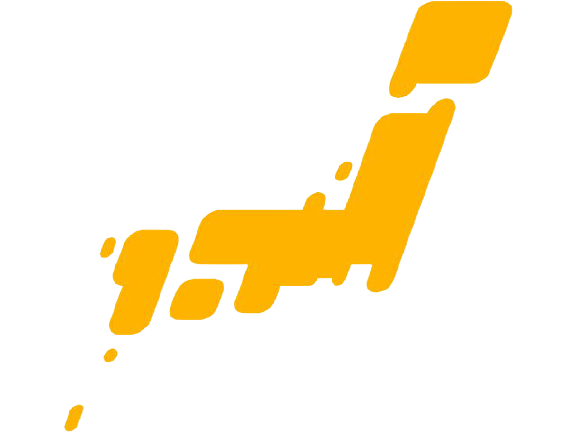 日本全国の駅
日本全国の駅
